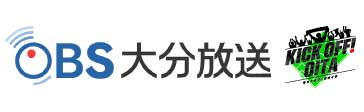一般社団法人大分県サッカー協会規約
第1章 総 則 (目 的) 第1条 本規約は一般社団法人大分県サッカー協会(以下「本協会」という)の定款第47条の規定に基づき、本協会の組織及び運営に関する基本原則を定める (遵守義務) 第2条 本協会の会員ならびに加盟登録した全ての団体及びその役員、監督、コーチその他の関係者、登録選手、審判員は本規約及びこれに付随する諸規定を遵守する義務を負う 第2章 目的及び事業 (目 的) 第3条 本協会は、大分県におけるサッカーの普及振興等を行うとともに、公益財団法人日本サッカー協会の事業に協力し、もってサッカーを通した大分県民の豊かなスポーツ文化の振興及び身心の健全育成並びに地域の活性化に寄与することを目的とする (事 業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う (1)サッカーの競技会の主催、主管、後援等に関すること (2)サッカーに係る団体、選手、監督及び審判の登録に関すること (3)サッカーの技術指導、研究及び調査並びに選手強化に関すること (4)サッカーの審判技術の研究及び審判員の養成に関すること (5)サッカーにおける医科学知識の普及及び向上に関すること (6)サッカーを通しての国際交流、地域間交流に関すること (7)サッカーに関する功労者及び優秀競技者の表彰に関すること (8)サッカーに関する広報及び普及に関すること (9)地域社会におけるサッカーグループの育成強化に関すること (10)サッカー施設の管理運営、拡充整備及び確保に関すること (11)サッカー以外のスポーツ団体と連携協力してスポーツの振興を図ること (12)その他この法人の目的を達成するために必要な事業 第3章 会 員 (会員の入会基準) 第5条 本協会に入会しようとするものは下記の事項に該当しなければならない (1)大分県内のサッカー愛好者であること (2)本協会の趣旨に賛同する個人又は団体であること (正会員の員数) 第6条 正会員総数は、各地区サッカー協会からあわせて50名以上、各種別・専門委員会及び事務局からあわせて20名以上、理事会において特に認めた者1名以上でなければならない (入会金及び会費) 第7条 本協会の入会金は、次のとおりとする (1)正会員 金 5,000円 (2)賛助会員 金 0円 (3)名誉会員 金 0円 2 本協会の会費は、次のとおりとする。 (1)正会員 金 5,000円 (2)賛助会員 ①個人会員 金 5,000円以上(1口) ②法人会員 金 10,000円以上(1口) ③パートナー会員 金 200,000円以上 ④プレミアムパートナー会員 金 500,000円以上 (3)名誉会員 金 0円 第4章 役員 (役員の選任等) 第8条 理事のうち、あわせて5名以上を種別・専門委員会及び事務局から選任しなければならない 2 理事及び幹事については、その就任時に満70才未満でなければならない。ただし、会長および副会長については理事会において特に承認が得られた者はこの限りでない 第5章 常務理事会 (常務理事会) 第9条 常務理事会は、会長、副会長、専務理事、常務理事をもって組織する 2 常務理事会は会長又は専務理事の要請によりその都度開催し、議長は会長がこれに当たる 3 3 常務理事会は次の事項につき協議する (1)理事会提出議案の作成に関すること (2)理事会決議事項の執行に関すること (3)その他理事会の決議を要しない常務に関すること 第6章 種別・専門委員会 (種別・専門委員会の設置) 第10条 本協会の事業遂行のため、次の種別・専門委員会を設置する (1)第1種委員会(社会人) (2)第1種委員会(大学) (3)第2種委員会(U-18) (4)第3種委員会(U-15) (5)第4種委員会(U-12) (6)キッズ委員会(U-10) (7)女子委員会 (8)シニア委員会 (9)フットサル委員会 (10)技術委員会 (11)審判委員会 (12)規律・裁定委員会 (13)医学委員会 (14)広報委員会 (15)eスポーツ委員会 (16)パラ委員会 (17)リスペクト・フェアプレー委員会 (18)青年部会 (組織及び委員) 第11条 各委員会は、それぞれ委員長及び委員をもって構成する 2 各委員長は各委員会の委員による互選により選出し、理事会の承認を得て会長が任命する 3 委員会の事業及び決定事項は、理事会に報告し、その承認を得なければならない (任 期) 第12条 各委員会の委員長及び委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する会議の終結の時までとし、再任を妨げない 2 委員長は、4回に限り再任されることができる 3 補欠又は増員により選任された委員長及び委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする 4 委員長及び委員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない (解 任) 第13条 委員長が次のいずれかに該当するときは、理事会に置いて出席した理事の3分の2以上の議決に基づき、当該委員長を解任することができる。この場合においては、議決する前に当該委員長に弁明の機会を与えなければならない (1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき (2)職務上の義務違反その他委員長たるにふさわしくない行為が認めらわるとき (召集及び議長) 第14条 各委員会は、それぞれの委員長が招集し、その議長となる 2 各委員会の招集は、各委員に対し会議開催時日の7日前までに通知しなければならない ただし、緊急の必要があるときはこの限りではない (種別・専門委員会の業務) 第15条 各種別・専門委員会の主たる業務は次の通りとする (1)第1種委員会(社会人) ア. 登録種別第1種のうち社会人に関する事項 イ. 管理登録種別第1種のうち社会人に関する大会及び試合の管理 (2)第1種委員会(大学) ア. 登録種別第1種のうち大学・高専に関する事項 イ. 登録種別第1種のうち大学・高専に関する大会及び試合の管理 (3)第2種委員会(高校、クラブ) ア. 登録種別第2種に関する事項 イ. 登録種別第2種に関する大会及び試合の管理 (4)第3種委員会(中学、クラブ) ア. 登録種別第3種に関する事項 イ. 登録種別第3種に関する大会及び試合の管理 (5)第4種委員会(ジュニア) ア. 登録種別第4種に関する事厦 イ. 登録種別第4種に関する大会及び試合の管理 (6)キッズ委員会 ア. 登録に関わらず10歳以下の年代に関する事項 イ. 登録に関わらず10歳以下の年代に関する事業の管理 (7)女子委員会 ウ. 登録種別女子サッカーに関する事項 エ. 登録種別女子に関する大会及び試合の管理 (8)シニア委員会 ア. 登録種別シニアに関する事項 イ. 登録種別シニアに関する大会及び試合の管理 (9)フットサル委員会 ア. 登録種別フットサルに関する事項 イ. 登録種別フットサルに関する大会及び試合の管理 ウ. フットサルの普及に関すること (10)技術委員会 ア. 競技技術の調査、研究ならびに指導に関すること イ. 技術講習会、研究会、練習会等の立案及び実施に関すること ウ. 指導者の研修及び派遣に関すること エ. サッカー競技指導要領の作成及び修正に関すること オ. 選手の育成強化方針及び対策に関すること カ. 選手の強化練習に関すること キ. 選手強化に伴う調査研究に関すること ク. その他選手強化に必要な事項に関すること ケ. 普及推進に関すること (11)審判委員会 ア. 各種競技会の審判員の編成及び割当並びに審判の実施に関すること イ. 審判技術の研修並びにその指導に関すること ウ. 公認審判員の推薦に関すること エ. 審判員の育成並びにそれに伴う事業の立案、実施に関すること オ. 競技規則の研究及び規則書の取扱に関すること カ. 審判員台帳及び公式審判員手帳の管理に関するごと キ. 審判員の登録に関すること (12)規律・裁定委員会 ア. JFAの定める規則等に対する違反行為のうち、競技会及び競技会に関するものについて調査、審議し、懲罰を決定する イ. JFAの定める規則等に対する違反行為のうち、競技会及び競技会に関するもの以外の違反行為について調査、審議し、懲罰を決定する (13)医学委員会 ア. サッカー競技者の傷害に対する処置と予防に関すること イ. 代表候補選手及び代表選手の体力向上に関すること (14)広報委員会 ア. 協会の広報・広聴業務に関すること イ. 協会内の組織伝達業務の統括に関すること ウ. サッカーファミリー拡大のために必要な広報・広聴のあり方の検討に関すること エ. 県協会の歴史の編纂に関すること (15)eスポーツ委員会 ア. eスポーツサッカーによるサッカーファミリーの獲得に関すること イ. eスポーツサッカーの大会及びイベントに関すること (16)パラ委員会 ア. 障がい者がサッカーを楽しめるための環境の整備に関すること イ. 障がい別団体の広報及び普及促進に関すること (17)リスペクト・フェアプレー委員会 ア. リスペクト宣言、JFAサッカーファミリー安全保護宣言、JFAセーフガーディングポリシーの周知、実践に関すること イ. ウェルフェアオフィサーの養成、研修及び派遣に関すること (18)青年部会 ア. 協会内の連携促進に関すること イ. サッカーファミリーの拡大を目指す取組に関すること ウ. 協会内の課題に対する改善案の立案・提言に関すること エ. 他団体等との連携を図りながら社会貢献に関すること (細則の制定) 第16条 各委員会は、その所管事項に関し、理事会の承認を得て、細則を制定することができる 第7章 事務局 (業 務) 第17条 事務局の主たる業務は次の業務とする (1)関係文書の収受及び発信並びに保管、整理に関すること (2)各種会議の招集及びその準備に関する事務並びに議事録の管理に関すること (3)各種別・専門委員会の連絡調整に関すること (4)渉外及び一般報道に関すること (5)本協会の予算案の作成及び決算報告に関すること (6)本協会の事業計画及び事業報告に関すること (7)規約、規則等の改廃、研究、企画に関すること (8)長期財政計画に関すること (9)本協会の資産の管理及び金銭出納に関すること (10)各種事業の収入及び支出に関すること (11)役員名簿、加盟団体名簿、登録票の保管及び手続きに関すること (12)会費、登録料の徴収簿の管理に関すること (13)(公財)日本サッカー協会、九州サッカー協会登録金及び大分県体育協会加盟金の納入に関すること (14)協会の公印及び備品等の保管に関すること (15)その他、一般庶務に関すること (備付帳簿及び書類) 第18条 事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を備え置かなければならない (1)定款及び規約 (2)会員名簿及び会員の移動に関する書類 (3)理事、監事及び職員の名簿及び履歴書 (4)処務日誌 (5)許可、認可等及び登記に関する書類 (6)定款に定める機関の議事に関する事項 (7)収入支出に関する帳簿及び証拠書類 (8)資産台帳、負債台帳及び正味財産の状況を示す書類 (9)官公署往復文書 (10)その他必要な書類及び帳簿 第8章 地区協会 (定 義) 第19条 地区協会とは、県下の各地区におけるサッカー界を統括し、当協会と協力関係の下、各地区におけるサッカーの普及及び振興を図る目的で組織された団体をいう (地区協会の組織) 第20条 地区協会は、次の機関および組織を保有する。 (1)決議機関 (2)執行機関 (3)種別・専門委員会(本協会の種別・専門委員会に準じた組織および機能を有すること) 第9章 加盟及び登録 (加盟チーム) 第21条 加盟チームとは、(公財)日本サッカー協会が制定したサッカー競技規則に基づきサッカー を行うチームであって、本章の定めるところにより本協会に加盟したものをいう (加盟チームの種別) 第22条 加盟チームの種別は次の通りとする (1)第1種 年齢を制限しない選手により構成されるチーム (2)第2種 18歳未満の選手により構成されるチーム ただし、高等学校在学中の選手には、この年齢制限を適用しない (3)第3種 15歳未満の選手により構成されるチーム ただし、中学校在学中の選手には、この年齢制限を適用しない (4)第4種 13歳未満の選手により構成されるチーム ただし、小学校在学中の選手には、この年齢制限を適用しない (5)女 子 女子の選手により構成されるチーム (6)シニア 40歳以上の選手により構成されるチーム 2 前項に定める年齢は、当該年度の開始日の前日(3月31日)現在の年齢とする ただし、シニアの種別については、当該登録年度最終日(3月31日)現在の年齢とする (加盟登録) 第23条 本協会に加盟登録しようとするチームは、大分県内にその本拠を有するものでなければならない 2 本協会に加盟登録しようとするチームは、地区協会単位で本協会に登録しなければならない (加盟登録の手続き) 第24条 (公財)日本サッカー協会に加盟登録しようとするチームは、KICKOFFサイトから登録申請をして、その承認を得なければならない (加盟チームの権利及び義務) 第25条 加盟チームは次の事項に関する権利を有する。 (1)地区協会の単位組織としてその施策に関与すること (2)県内の公式競技会に出場すること(ただし、外国国籍選手の参加については、各競技会要項の定めるところによる) 2 加盟チームは次の事項を遵守しなければならない (1)登録する場合は必ず規定の登録料を納入すること (2)(公財)日本サッカー協会の機関誌(有料)を購読すること (3)(公財)日本サッカー協会の機関誌に監督登録料を納付すること (4)毎年第27条以下に定めるところにより、選手指名その他所要事項を登録すること (5)公益財団法人日本サッカー協会「ユニフォーム規定」に定める規定を遵守すること (加盟チームに対する制裁) 第26条 加盟チーム及び選手が規定の資格を失い、又は規定に違反した場合は、理事会及び総会の決議を経て、加盟及び登録を取り消すことができる (選手登録) 第27条 加盟チームは、第29条の定めるところにより、本協会への選手登録を行わなければならない 2 本協会に登録されている選手に限り公式競技に出場することができ、未登録の選手を公式競技に出場させてはならない (重複登録の禁止) 第28条 選手は2つ以上の加盟チームに登録することはできない (サッカーチームとフットサルチームの重複登録を除く) (選手登録の方法) 第29条 本協会への登録はKICKOFFサイトから行う 2 登録を削除、追加または内容を変更する場合は、チーム登録責任者もしくはその代理が、すみやかにKICKOFFサイトから行わなければならない (フットサル登録) 第30条 フットサル登録については、(公財)日本サッカー協会「フットサル登録制度について」に定めるところによる (登録加盟費) 第31条 本協会に加盟登録しようとするチームは下記の区分に応じて本協会に登録加盟費を納入し なければならない (1)第1種 J・JFL 33,000円+2,900円×登録人数 社会人チーム 29,000円+2,900円×登録人数 九州社会人連盟費 6,000円/1チーム 大学チーム 26,000円+2,500円×登録人数 高専チーム 21,000円+2,500円×登録人数 (2)第2種 高校チーム 17,500円+1,700円×登録人数 (3)第3種 中学チーム 13,500円+ 900円×登録人数 (4)第4種 少年チーム 13,700円+ 900円×登録人数 (5)女子 第1種 18,000円+2,500円×登録人数 第2種 14,000円+1,500円×登録人数 第3種 13,500円+ 900円×登録人数 (6)シニア 15,500円+2,200円×登録 (7)監督登録料 全チーム 2,000円 (8)機関紙購読料 全チーム 5,000円 第10章 審判 (公式試合の審判) 第32条 (公財)日本サッカー協会及び本協会に登録された審判員(以下「審判員」という)以外の者は県内の公式試合の審判を行うことはできない (資格の種類) 第33条 審判員の資格は次の9種類とする (1)1級審判員 (2)女子1級審判員 (3)2級審判員 (4)3級審判員 (5)4級審判員 (6)フットサル1級審判員 (7)フットサル2級審判員 (8)フットサル3級審判員 (9)フットサル4級審判員 (資格の認定) 第34条 3級、4級、フットサル3級審判員及びフットサル4級審判員の資格は、(公財)日本サッカー協会の審判委員会の指導を受けて、本協会が主催する認定講習会を経て的確と認めた者に対して与える (新規登録) 第35条 新規に資格を認定された審判員は本協会に新規登録の事務手続きを行い、所定の登録料を納入する (更 新) 第36条 審判員は毎年所定の研修会あるいは更新講習会を受講し、資格を更新することができる 2 審判員として更新しようとするものは、更新登録料を納入しなければならない 第11章 大会運営 (大会参加料) 第37条 大会参加料は、本協会が主催する大会ごとに当該参加するチームから徴収するものとし、上限を30,000円とする なお、フットサルについては別途定める 第12章 資産及び会計 (資産の構成) 第38条 本協会の資産は、次に掲げるものをもって構成する (1)別紙財産目録に記載された財産 (2)入会金及び会費 (3)寄附金品 (4)財産から生ずる収入 (5)事業に伴う収入 (6)その他の収入 (財産の管理) 第39条 本協会の財産は会長が管理し、その管理方法は、総会の議決に基づき会長が管理する 第13章 規約の変更 (規約の変更) 第40条 本規約は、理事会決議の3分の2以上の同意を得なければ、これを変更することができない 第14章 補 則 (細 則) 第41条 この規約においての細則は、理事会において別に定める 附則 1 この規約は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定 等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同 法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する 附 則 この規約の変更は、2017年5月28日から施行する この規約の変更は、2019年5月26日から施行する この規約の変更は、2020年6月 1日から施行する この規約の変更は、2021年5月31日から施行する この規約の変更は、2022年5月29日から施行する この規約の変更は、2024年5月29日から施行する